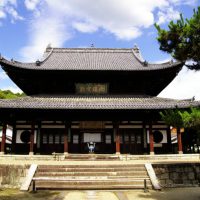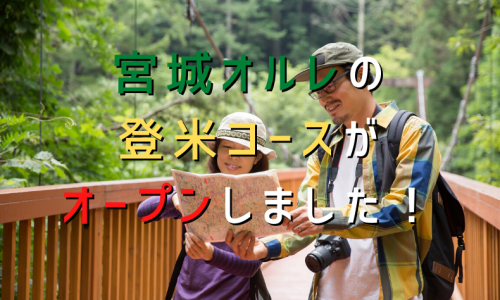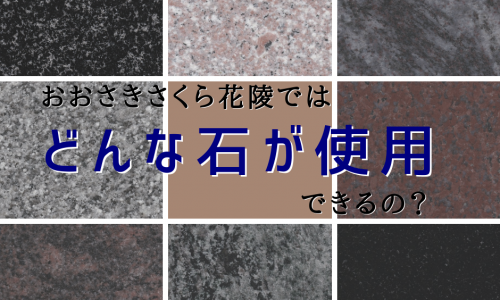お墓は、故人やご先祖様が眠っているところです。感謝の気持ちを伝えるために、お墓参りに行かれる方は多いと思いますが、お墓参りに行く時期に迷うこともあるようです。
今回は、お墓参りに行く時期の目安にしたい仏教の年中行事について、くわしくご紹介します。
仏教の年中行事
地域によって時期が違う場合もありますが、仏教での年中行事は次のものがあります。
・1月
<修正会(しゅしょうえ)>
年初めの3日もしくは7日間にわたって、国家・皇室の安泰、五穀豊穣などを祈願する法会のことです。また、前年の罪や過ちを悔い改め、新年をお祝いする行事で元旦会と呼ぶこともあります。
・2月、3月
<涅槃会(ねはんえ)>
お釈迦様の命日に行われる法会のことです。旧暦の2月15日に行う地域や、今の暦の3月15日に行う地域があります。
<春彼岸会(はるひがんえ)>
春分の中日を挟んだ前後7日間のことです。彼岸の期間にはお墓参りをしたりお経をあげてもらう方が多くなります。
・4月
<灌仏会(かんぶつえ)>
お釈迦様の誕生日を祝う法会のことです。灌仏会の他に、花祭りや仏生会、降誕会など様々な呼び方をします。一般的に4月8日に行われることが多いですが、5月8日に行う地域もあります。
・8月
<盂蘭盆会(うらぼんえ)>
8月15日(7月15日)
ご先祖様を祀る行事で、お盆、盆会、精霊会、魂祭、歓喜会などと呼ばれます。日本では1番お墓参りに行く方が多い時期です。7月15日に行う地域もありますが、全国的には8月15日に行うことが多いとされています。
・9月
<秋彼岸会(あきひがんえ)>
秋分の日を挟んだ前後7日間のことです。彼岸の期間にはお墓参りをしたりお経をあげてもらう方が多くなります。
・12月
<成道会(じょうどうえ)>
12月8日
お釈迦さまがインド・ブッタガヤの菩提樹の下で悟りを開いた日を記念して行われる法会のことです。成道会の他に、臘八会(ろうはちえ)と呼ばれることもあります。
・その他
<祥月命日(しょうげつめいにち)>
命日と同じ月日のことです。この他にも命日と同じ日のことを月命日と呼びます。盂蘭盆会と同様に、お墓参りに行く方が多く故人を偲ぶ日です。
<まとめ>
結論から言うと、お墓参りをしてはいけない時期はありません。よく耳にする「仏滅にお墓参りしてはいけない」というのは、根拠のない迷信でお墓参りはいつ行っても構いません。
お墓参りには、祥月命日やお彼岸、お盆などに行かれる方が多いと思いますが、その他の年中行事が行われる時期にもお墓参りしてはいかがでしょうか。