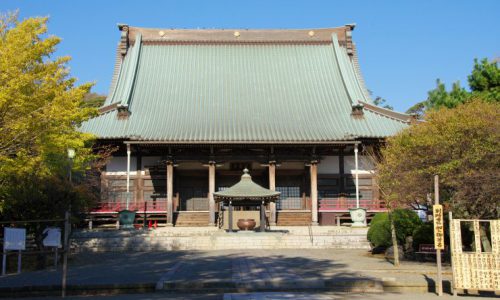お盆と言えばご先祖様のために、迎え火や送り火を焚く地域も多いです。
そんな迎え火と送り火ですが、具体的にはいつ、何時ごろに焚くのが良いのでしょうか?
今回は、気になる迎え火と送り火の基本について、くわしくご紹介いたします。
迎え火と送り火とは?
お盆の入りにご先祖様をお迎えする際の目印として焚くのが「迎え火」です。
それに対し、ご先祖様が極楽浄土へ旅立ちになる際に私たちがここでしっかりと見送っている証として焚くのが「送り火」。
この迎え火や送り火ですが、地域によって玄関やお墓など行う場所もさまざまです。
また、お墓で迎え火や送り火をする場合は、お墓参りが終わったあと迎え火として提灯に灯りを灯します。
その提灯を持ち運んで、ご先祖様を自宅まで導いているのです。
ちなみに迎え火や送り火を行わない地域もあり、盆提灯を精霊棚のところに置いてご先祖様が帰ってくる際の目印にしています。
迎え火と送り火は何日に用意するの?
・迎え火
迎え火は盆入りである8月13日の夕方ごろに行うのが一般的ですが、地域によってはその前日の12日に迎え火を焚くところもあります。
家の玄関や門口で、焙烙(ほうろく)という素焼きの平皿におがらを置いて燃やします。
このおがらはスーパーやホームセンターで購入できますが、もし焙烙がない場合は耐熱用のお皿を用いることも可能です。
・送り火
一方送り火はお盆明けの16日に行います。
このとき迎え火と同じ場所で、同じようにおがらで火を焚いてご先祖様をお見送りします。
また、お盆の精霊棚に飾ってあったナスの牛やキュウリの馬の乗り物があれば、おがらと一緒に燃やしましょう。
乗り物やおがらを燃やした煙に乗って、ご先祖様は極楽浄土へ行かれるのです。
迎え火や送り火ができないときはどうするべき?
近年はマンションやアパートなどの集合住宅にお住まいの方も多いですよね。
その場合、迎え火や送り火を玄関やベランダで焚くのは周辺の方にご迷惑がかかることもあるでしょう。
このときは迎え火や送り火の代わりとして、盆提灯を飾ればご先祖様はそれを目印として家に帰ってくることができます。
迎え火の代わりとして、13日には灯した盆提灯を持って玄関先やベランダに立って一礼後黙とうを捧げましょう。
また、送り火の際も同じくご先祖様をお見送りするために、迎え火と同じ場所で盆提灯に明かりを灯し、一礼して黙とうを行います。
<まとめ>
迎え火や送り火の火をまたいで病気から身を守るという風習や、お経を唱える地域など細かい違いがあります。
また、迎え火や送り火を行わない地域もあるなどお盆の過ごし方には大きな違いがあります。
しかし、地域差はあってもお盆は年に一度ご先祖様が家に帰ってこられる大切な時期。
ぜひ家族みんなでご先祖様の冥福をお祈りし日々の感謝をお伝えしたいですね。